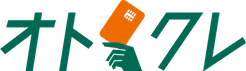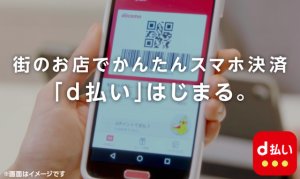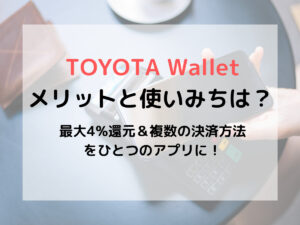PayPay、LINE Payをはじめとした「Pay(ペイ)サービス」は、今や日常で欠かせないキャッシュレス決済のひとつとなっている。
本記事では数多あるPayサービスを可能な限り網羅して、その種類と概要を整理。
QRコード決済と一緒にされることが多いApplePayなど周辺のサービスも合わせて紹介するので参考にしてほしい。
目次
Payサービス一覧
「Payサービス」と呼ばれる決済サービスには、大きく次のような分類がある。これらはまとめて「スマホ決済」と呼ばれることもある。
- バーコード決済/QRコード決済:専用アプリでバーコードやQRコードを読み取る。
- 非接触決済:対応しているカードやスマホなどの端末を決済端末にかざす。
- その他:専用アプリからバーチャル/リアルカードを発行、アプリで利用の設定・管理。
このなかでPayサービスの主流は、「バーコード決済/QRコード決済」だ。本記事でも「バーコード決済/QRコード決済」に焦点をあてて紹介する。
まずは現状登場している主要なPayサービスの種類を下表で確認しておこう。なお、同じ分類のサービスでも「Pay」とつかないサービスもある。
QRコード決済一覧表
| 一般系 | PayPay(ペイペイ) LINE Pay(ライン ペイ) 楽天ペイ d払い au Pay メルペイ |
|---|---|
| ネット・通販系 | Amazon Pay atone |
| 独自+一般系 | ANA Pay TOYOTA Wallet |
| 独自系 | ファミペイ UNIQLO Pay |
| 金融系 | ゆうちょPay J-Coin Pay PayB Payどん はまPay |
| 送金系 | Pring(プリン) QUOカードPay |
| 海外系 | AliPay WechatPay |
【QRコード決済の種類分け】
- 一般系:実店舗を主体に広く普及、ネット通販にも対応している
- ネット・通販系:ネット通販を主体に普及、実店舗決済にも対応している場合も
- 独自+一般系:提供元の店舗での独自サービスの他、一般的な店舗にも加盟店がある
- 独自系:提供元の店舗での決済に利用できたり特典がついたりする
- 金融系:金融機関が主体となって提供。銀行口座と紐づけて利用する
- 送金系:個人間の送金などを主体とした機能展開。実店舗・ネット決済にも対応している
- 海外系:海外のサービス。国内でも訪日外国人客の利用ニーズがある
分かりやすくするため、上記のように分類しているが、Payサービスは日々進化しており、独自系のサービスでも使える店が増えるなどの変化がある。
QRコード決済以外のPayサービス
QRコード決済以外にも、「Pay」とつくサービスや類似サービスとして以下のようなサービスがある。
| 非接触決済 | Apple Pay Google Pay QUIC Pay | |
|---|---|---|
| その他 | Kyash バンドルカード | |
Payサービス比較表と分類一覧
今回紹介するQRコード決済サービス(Payサービス)の支払い方法と特徴的な機能を下表にまとめた(2019年6月時点)。
支払い方法としては、事前チャージかクレジットカード払いまたは銀行口座紐づけのいずれかが基本だ。
| サービス名称 | 支払い方法 | チャージ方法 | 特徴的な機能 |
|---|---|---|---|
| PayPay | PayPay残高(事前チャージ) クレジットカード | 銀行口座 セブン銀行ATM ヤフオク!・PayPayフリマの売上金 PayPayカード(旧ヤフーカード) ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い | わりかん機能 払込票のバーコード読み取り可能 |
| LINE Pay | LINE Pay残高(事前チャージ) Visa LINE Payクレジットカード 三井住友カード | 銀行口座 セブン銀行ATM QRコード/バーコード(一部店舗) LINE Pay カード Fami ポート 東急線各駅の券売機 オートチャージ | 個人間送金 割り勘機能 払込票のバーコード読み取り可能 |
| 楽天ペイ | 楽天ポイント 楽天キャッシュ(事前チャージ) クレジットカード | 楽天キャッシュ 楽天カード 楽天銀行 ラクマ売上金 楽天Edy 楽天ペイのSuica | 個人間送金 楽天アカウントで他サイトにもログイン |
| d払い | 電話料金合算 クレジットカード d払い残高 dポイント | 銀行口座 セブン銀行ATM コンビニ | 個人間送金 払込票のバーコード読み取り可能 |
| au PAY | au PAY 残高(事前チャージ) クレジットカード | 現金 auかんたん決済 Pontaポイント クレジットカード auじぶん銀行 銀行口座 au PAY スマートローン au PAY ギフトカード | 個人間送金 払込票のバーコード読み取り可能 |
| メルペイ | メルペイ残高(事前チャージ) メルカリ売上金 ポイント | 銀行口座 セブン銀行ATM | iD決済も利用可能 |
| Amazon Pay | クレジットカード | – | Amazonアカウントで他サイトにもログイン |
| atone | 請求書払い コンビニ払い 口座振替 | – | 一カ月分まとめての後払い |
| ANA Pay | 事前チャージ(JCB) | クレジットカード(JCB) | ANAマイルが貯まる |
| TOYOTA Wallet | TOYOTA Wallet残高(事前チャージ) 後払い(クレジット) 銀行口座(即時引き落とし) | クレジットカード 銀行口座 | 3つの決済サービスがまとまっている |
| ファミペイ | FamiPay事前チャージ | 現金 クレジットカード 銀行口座 | ファミペイで使えるクーポン配信 対応払込票のバーコード読み取り可能 |
| UNIQLO Pay(ユニクロペイ) | 銀行口座 クレジットカード | – | – |
| ゆうちょPay | ゆうちょ銀行口座(即時払い) | – | 対応払込票のバーコード読み取り可能 |
| J-Coin Pay | 事前チャージ | 銀行口座 | 個人間送金 口座にお金を戻せる |
| PayB | クレジットカード 銀行口座(即時払い) | – | 対応払込票のバーコード読み取り可能 |
| Pring | 事前チャージ | 銀行口座 | 個人間送金 |
なお、各サービスのポイント還元については、以下記事で解説しているので、合わせて参考にしてほしい。
主要なPayサービス
PayPay(ペイペイ)
ソフトバンクとヤフーが共同で設立したPayPay株式会社が運営している。
2018年12月、2019年1月に開催した「100億円あげちゃうキャンペーン」で認知度、利用者数ともに急上昇。PayPayに追従する形で、各社が10%、20%などの還元キャンペーンを展開するようになった。
QR決済のリーディングカンパニーといえる。決済手数料無料のキャンペーンを開催したことで、加盟店も増えている。
支払いは、事前にチャージしたPayPay残高もしくは登録クレジットカードを利用する。PayPay残高へのチャージは、銀行口座やPayPayカード(旧ヤフーカード)などからできる。
また、ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払いや、ヤフオク!の売上金などがチャージに利用できるのも特徴的だ。
利用額に応じたポイント(PayPayポイント)還元があり、PayPay残高もしくはPayPayカード(旧ヤフーカード)での支払いであれば還元率0.5~1.5%となる。PayPayカード(旧ヤフーカード)以外のクレジットカードでは還元がない。
基本の還元率はPayPay残高払いで0.5%、PayPayカード払いで1.0%で、前月1日~末日の200円以上の決済回数50回以上および利用金額10万円以上で+0.5%となる。
「Yahoo!ショッピング」や「ヤフオク!」などヤフー関連サービスをはじめとしてオンライン決済にも対応している。
LINE Pay
LINE株式会社が運営する、コミュニケーションツール「LINE」と連携したサービス。コミュニケーションツールとしてのLINE利用者はかなりの数になる。
コミュニケーションアプリ「LINE」のウォレット機能から利用できる。リアル店舗、オンライン店舗ともに加盟店も増えている。
LINE Payの支払い方法は、クレジットカードもしくは事前チャージ。
クレジットカードは、Visa LINE Payクレジットカード(P+)/Visa LINE Payクレジットカードか三井住友カードを登録し、チャージ&ペイを利用するのが基本。
その他のVisa、マスターカードも登録はできるが、利用できる支払いが一部のLINEサービスに限定されており、LINE Payの支払いには使えない。
Visa LINE Payクレジットカード(P+)によるチャージ&ペイ利用時のみ、利用金額に応じたLINEポイントの還元があり、還元率は5.0%。
事前チャージは、銀行口座、コンビニなどで可能。銀行口座の利用でオートチャージも可能だ。
店舗でのQRコード決済のほかに、個人間送金と割り勘の機能、出金も可能である。
楽天ペイ
楽天グループの楽天ペイメント株式会社が運営するサービス。
楽天というとネットショッピングのイメージが強いかもしれないが、リアル店舗でも楽天ペイを利用できるところは多い。
また、楽天グループ以外のネットショップでも楽天ペイを利用できるところが増えている。
ネットショップでの利用では、楽天アカウントでログイン、楽天IDに登録したクレジットカード情報で支払いができる。
楽天ペイで楽天ペイを利用する場合は。クレジットカードのほか、楽天ポイントや楽天キャッシュで支払いが可能。
楽天カードや楽天キャッシュで支払えば、楽天ポイントの還元もある。もっともお得なのが、楽天カードで楽天キャッシュにチャージして、楽天キャッシュで支払うパターンだ。
キャンペーンもよく開催されており、期間中、条件に応じて通常ポイント以外の楽天ポイントの還元も受けられる。
楽天ポイントは1ポイント=1円相当として楽天関連サービスで利用できるため、楽天ペイは楽天ユーザーにメリットの大きいサービスと言える。
楽天Edyとは違う
楽天グループでは楽天ペイとは別に電子マネー「楽天Edy」も提供している。こちらは非接触型の決済サービスだ。
楽天ペイと楽天Edyとでは加盟店も異なる。楽天ペイアプリには楽天Edy機能も搭載されており、楽天ペイを利用することで2つのサービスを効率的に使い分けられる。
d払い
株式会社NTTドコモが運営するサービス。「Pay」とはついていないが、主要なQRコード決済サービスのひとつ。
ドコモユーザーに特に便利なサービスだが、ドコモユーザー以外でもお得に利用できる。リアル店舗、ネットショップともに加盟店を増やしている。
d払いでは利用金額に応じてdポイントが貯まる。リアル店舗では200円(税込)利用につきdポイントが1ポイント、ネットショップでは100円(税込)利用につきdポイントが1ポイント。
ただし、クレジットカードを支払い元に設定する場合、dカード/dカードGOLDのみがポイント還元の対象となる。
dポイントは加盟店舗での買い物に利用できる他、d払いでの支払いに充当することも可能。ドコモ回線利用でもdポイントが貯まるため、ドコモユーザーはdポイントを貯めやすい。
支払い方法として、事前チャージしたd払い残高やクレジットカードの他、ドコモユーザーであれば電話料金合算払いも利用できる。
クレジットカード払い以外の場合、d払いの利用上限は1万円/3万円/5万円から契約・利用状況に応じてドコモにより設定される。クレジットカード払いではカードの利用上限が適用される。
au PAY
KDDI株式会社が運営するサービス。auユーザーのみが対象となっていたが、2019年8月に非auユーザーも利用可能になった。
au PAY 残高により支払いを行い、事前に口座やクレジットカードなどでチャージが必要。
チャージ方法は、携帯電話料金との合算ができる「auかんたん決済」「au PAY カード」「auじぶん銀行」「コンビニATM」「Pontaポイント」「クレジットカード」がある。
1回あたりの支払い可能額は30万円。1日あたりの支払いは50万円まで利用ができる。
au PAYでは、利用金額に応じてPontaポイントが貯まる。基本はau PAY利用200円(税込)ごとに1ポイントだ。
Pontaポイントはau PAYの支払い、au PAY マーケット(au Wowma!)での利用、au携帯料金の支払い、商品や他ポイントとの交換のほか、リクルート系のサービスでも利用できるので使い道は広い。
メルペイ
株式会社メルカリが運営するサービス。フリマアプリ「メルカリ」から使うことができ、メルカリユーザー向けのサービスとなっている。
銀行口座からチャージした残高の他に、メルカリの売上金を支払いに使うことができるため、売上金を有効に使いたいメルカリユーザーにおすすめ。
また、メルペイ加盟店でのQRコード決済の他にiD決済も利用でき、使える店が実は多いサービスでもある。ネット通販の加盟店も多数。
ネット・通販系
Amazon Pay
Amazonの運営するサービス。AmazonアカウントでAmazon以外のネットショップにもログイン、Amazonアカウントに登録したクレジットカードで支払いができるサービスとしてリリースされた。
Amazon Pay対応サイトでは、はじめて利用するサイトでも新規会員登録等の手間がなく、最短2クリックで買い物が完了するという便利なサービス。
その後、2018年にリアル店舗でのQRコード決済にも対応するようになった。
ただし、Amazon Pay専用のアプリはなく、AmazonショッピングアプリでQRコードを表示させ、店舗側の端末で読み取るという形。このQRコードの表示が、専用アプリを持つ他のサービスに比べるとややわかりにくい。
QRコード決済としては後発だが、Amazon Payを導入しているネットショップは非常に多い。今後、リアル店舗での利用がどの程度広まるか注目だ。
atone(アトネ)
株式会社ネットプロテクションズが運営するサービス。
ネットプロテクションズは、ネットショップの後払いサービスとして有名な「NP後払い」を運営する会社で、信頼度が高い。
atoneもスマホアプリを使ったネットショップでの後払いサービスがベースだが、対応しているリアル店舗でのQRコード決済にも対応している。
他のサービスと大きく違うのが、1カ月分の利用金額がまとめて請求されるという点。利用上限は月最大5万円。
支払い方法は、請求書払い、コンビニ払い(Loppi/Famiポート等)もしくは口座振替。請求書払いとコンビニ払いは毎月20日、口座振替は毎月27日が支払い日となる。
請求があった月にのみ若干の請求費が発生し、ネットショップ利用では90円、QRコード決済では97円となる。
利用金額に応じてNPポイントが貯まり、支払いの際の値引きや、さまざまなサービスとの交換が可能。
独自+一般系
ANA Pay
ANAマイレージクラブアプリから使えるQRコード決済サービス。ANA PayまたはSmart Code加盟店での利用が可能。
利用金額に応じてANAマイルが貯まる。チャージはJCBブランドのクレジットカードからのみ可能。
ANA JCBカードからのチャージや、ANA Payマイルプラス加盟店での利用で、通常のマイル付与にさらにマイルが加算される。
ANAマイルを効率的に貯めたい人におすすめだ。
TOYOTA Wallet
トヨタファイナンシャルサービス株式会社が運営するスマホ決済サービス。以下いずれかの方法で決済ができる。
| iD/Mastercard残高 | iD加盟店・Mastercard®コンタクトレス加盟店で利用できる電子マネーでの支払い |
|---|---|
| 銀行Pay | コード支払いで利用できる銀行口座即時引き落とし払い |
| Bank Pay | コード支払いで利用できる銀行口座即時引き落とし払い |
| QUICPay残高 | QUICPayを利用、トヨタファイナンス発行のクレジットカードによるチャージまたは即時払い |
| Wallet QR | トヨタ販売店で利用できるコード支払い |
独自系
ファミペイ
株式会社ファミリーマートが運営するバーコード決済サービス。2019年7月にリリースされた。ファミリーマートで使える。
200円(税込)の利用につき1円分のFamiPayボーナス付与、ファミリーマートでサービス商材(収納代行・Famiポート等)を支払う場合は1件につき10円分のボーナスが付与される。
利用金額に応じて還元される通常ボーナスと、キャンペーンで付与される期間限定ボーナスとがあり、有効期限が異なるが、いずれも残高に自動的に加算される。
事前チャージが必要で、現金・銀行口座・クレジットカード(JCBブランド)でチャージができる。
2019年11月には、dポイント、楽天スーパーポイント、Tポイントと連携して、ファミペイ上で3つのポイントが使えるようになった。
UNIQLO Pay
ユニクロアプリから利用できるQRコード決済サービス。2021年にリリースされた。ユニクロのセルフレジで使える。
支払い方法は銀行口座もしくはクレジットカード。チャージの仕組みはない。
ユニクロ店舗での支払いをスピーディーに済ませることができる。
金融系
金融系のPayサービスは、他のPayサービスと色合いはやや異なっている。
金融系は現在、GMOペイメントグループが提供する銀行Payを利用したPayサービスと、みずほ銀行が開発したJ-Coin Payの勢力がある。
銀行PayはゆうちょPayを始め、各銀行に決済プラットフォームを提供している仕組みとなっている。
提携する銀行口座を紐づけ、支払いを行うので、クレジットカードを持たない人にも便利だ。
ゆうちょPay
株式会社ゆうちょ銀行が運営するサービス。
QRコード決済だけでなく、対応している払込票のバーコード等を読み取りによる支払いができる。
対応している払込票であれば、ネットショップや公共料金等の支払いも可能。
ゆうちょ銀行口座にひもづき、口座即時引き落としで支払いとなる。1日あたり200万円、1カ月あたり500万円を利用上限として、口座残高の範囲内で利用可能。
ゆうちょPayはGMOペイメントグループが提供する「銀行Pay」と呼ばれる決済プラットフォームを利用している。
ゆうちょPay以外にも、横浜銀行が運営する「はまPay」や、熊本銀行が運営する「YOKA!Pay」など、各地方銀行にも同様なPayサービスが展開されつつある。

J-Coin Pay
みずほ銀行が提供するスマホ決済サービス。サービス自体はすでにローンチしているが、加盟店の参加は進んでいないようだ。
銀行口座からチャージして利用できるほか、残高を銀行口座に戻すことも出来る。また、提携した銀行間での送金も無料で可能になる。
2019年6月現在、地方銀行を中心に50行が参加している。
Payどん
鹿児島銀行が独自開発したPayサービス。
PayB
ビリングシステム株式会社が運営するサービス。
QRコード決済だけでなく、対応している払込票のバーコード等を読み取りによる支払いができる。
対応している払込票であれば、ネットショップや公共料金等の支払いも可能。
支払い方法はクレジットカードもしくは銀行口座からの即時払い。
利用上限は1回あたり最大30万円で、1日の利用上限も30万円。
送金系
Pring(プリン)
株式会社pringが運営するサービス。「Pay」とはついていないが、QRコード決済サービスのひとつ。
個人間送金アプリとしてリリースされたが、リアル店舗での利用もできるようになった。
個人間送金はアプリ内もしくはQRコード利用でも行うことができ、利便性が高い。リアル店舗での利用は他のサービスと同様。
支払い方法は銀行口座からの事前チャージ。入金の上限金額が1日あたり100万円、出金及び送金の上限金額が1日あたり10万円となっている。
QUOカードPay
株式会社クオカードが運営するデジタルギフトサービス。
企業のプロモーションやキャンペーンなどで受け取ることができる。
企業やキャンペーンごとにデザインが違い、見る楽しさもある。
送られてきたURLをスマートフォンで開くとギフトを受け取ることができる。
そのURLからバーコードを表示し、お店の人に読み取ってもらえば決済が完了する。
全国のローソンのほか、大手ドラッグストアや飲食店でも導入されている。
番外編!非接触型のPayサービス
本記事では、基本的にQRコード決済のできるPayサービスを紹介してきたが、「Payサービス」として一緒に紹介されることの多いサービスも、参考に紹介しておく。
Apple Pay
Apple製のデバイスで利用できるPayサービス。日本国内で使用されているほぼすべてのクレジットカードやプリペイドカードを紐づけることができる。
ポイントカードやギフトカードも含め8枚まで登録可能で、アプリ内で任意のカードを瞬時に切り替えて使えるため非常に便利だ。ポイントも引き継がれ、特典なども同じように利用できる。
iPhone 7以降のiPhoneか、Apple Watch Series 2以降のApple Watchでは、交通系ICカードの「Suica」を追加できるようになり、話題を呼んだ。
SuicaへのチャージやSuica定期券の更新も、アプリ内で手軽に済ませられる。
店頭での支払に利用する際は、専用の端末にスマホをかざすだけで決済が完了する。iPhone、iPad、Touch IDを搭載したMacBook Proでは、Touch IDで支払いも可能。
Google Pay

Googleが提供するAndroidスマートフォン向けの決済方法。以前は「Andoroid Pay」というサービス名だったが、2018年2月20日よりGoogle Payに変更された。
電子マネーを登録し、クレジットカードでチャージをすることで、電子マネーの利用をスマートフォンにまとめることができる。
Google Payに紐付けできる対象の電子マネーは楽天Edy、nanaco、WAON、Suicaだ。
対応している店舗に入店した際には知らせてくれるサービスもあり、非常に便利だ。Androidユーザーなら活用しない手はないだろう。
QUIC Pay(クイックペイ)
QUIC Payを搭載したカードやおさいふケータイ対応の携帯電話などを専用端末にかざすだけで支払いができる電子マネー。
カードタイプ、モバイルタイプ、キーホルダーなどのタイプがある。
支払いは対応するクレジットカード・デビットカード・プリペイドカードで可能。QUIC Pay搭載のクレジットカードも多い。1回あたりの利用金額は2万円まで。
キャッシュレス決済をお得に使おう
今回紹介したようなPayサービスが登場したことで、キャッシュレス決済はさらに進んでいる。
QRコード決済は、スマホにアプリをダウンロードして簡単な設定を行うだけで利用できるので、クレジットカードよりも多くの人が利用できる。
また、クレジットカードに比べて加盟店の手数料負担が抑えられることも、利用が進んでいる大きな要因だろう。
キャッシュレス決済、特にQRコード決済は今後さらに普及していくのではないだろうか。
一方、QRコード決済の支払いにはクレジットカードをひもづけられるサービスが多い。
クレジットカードを持っていて利用に抵抗がないのならば、QRコード決済の支払いをカードで行うことでポイントを効率的に貯めることができる。
QRコード決済は、サービスによって独自のポイントを付与している場合もあり、ポイントの二重取りが可能だ。
QRコード決済は1回あたりの利用上限が高くないサービスもあるので、少額の支払いをQRコード決済で、まとまった支払いはクレジットカードで行うというように、場面ごとに適切な決済方法を使い分けるのもおすすめだ。
また、QRコード決済以外に、非接触型決済で「○○Pay」と呼ばれるサービスもある。決済の手間という点では、このサービスが一番手間がかからない。非接触型の決済サービスもクレジットカードを紐づけることが多い。
最後に、QRコード決済サービスは、期間限定でお得なキャンペーンを行っていることが多いので、利用の際はそういったキャンペーンもチェックしてお得に活用しよう。