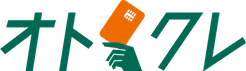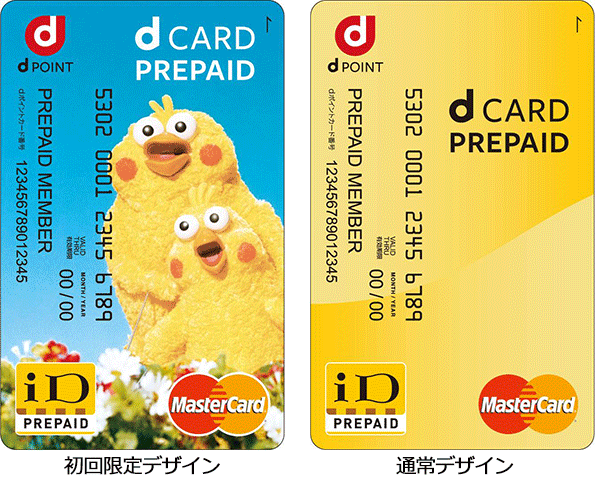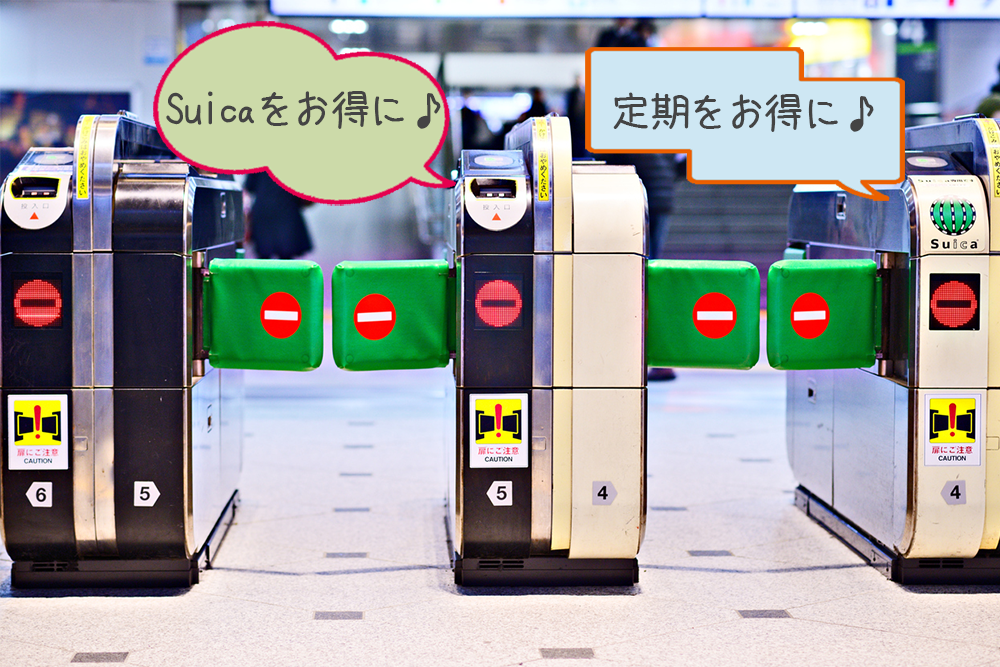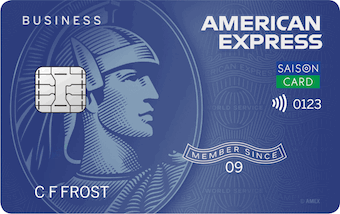2022年6月30日よりスタートした第2弾マイナポイント事業。
マイナンバーカードを発行し、所定の手続きおよび選択したキャッシュレス決済サービスを利用すると、ポイントが最大20,000円分もらえるというもの。
本記事では、マイナポイントを利用するために必要な手続きを、マイナンバーカード発行の方法から詳しく紹介する。
目次
マイナポイント事業とは
マイナポイント事業は、総務省主導のマイナンバーカード利用推進のための事業だ。マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)が記載されたプラスチック製カードのこと。マイナンバーは12桁の番号で、日本に住民票を有するすべての人が持っている。
マイナポイント事業は、2020年9月~2021年12月31日に第1弾が実施され、2022年6月30日から第2弾が実施されている。第2弾は以下3つの施策からなる。
- 施策1:マイナンバーカード新規取得、対象決済サービス利用で最大5,000円分ポイント
- 施策2:マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込で7,500円分のポイント
- 施策3:公金受取口座の登録で7,500円分のポイント
施策1は第1・2弾共通、施策2・3は第2弾で新たに始まったものだ。
第1・2弾の共通施策
第1弾のマイナポイント事業では、マイナンバーカードを利用して所定の手続きを行い、対象のキャッシュレス決済サービス1つを選択すると、対象期間中、選択したキャッシュレス決済利用時に最大25%(上限5,000円分)のポイントが還元された。
第2弾でも、第1弾でこの申込を行っていない人を対象に、同じ施策が実施されている(施策1)。
また、第1弾に申し込んだ人でも、第1弾期間中に上限5,000円分までのポイント付与を受けていなかった場合、第2弾で新たに残りの上限までのポイント付与を受けることができる。
どのキャッシュレス決済サービスを選択するかによって還元されるポイントは異なるが、この事業で還元されるポイントを総称して「マイナポイント」と呼んでいる。
決済サービスの変更はできないが例外あり
基本的には、一度選んだ決済サービスは変更できないが、第1弾で対象となっていた決済サービスが第2弾で対象外(受付終了)となっている場合があり、その場合のみ第1弾と異なる決済サービスを新たに選択できる。
第2弾の新たな施策
マイナポイント第2弾では、第1弾と共通の施策1に加えて、新たに2つの施策が実施されている。第2弾ではじめて施策1に申し込んだ場合、施策2・3でもらえるポイントは施策1で選んだ決済サービスのものとなる。
第1弾ですでに申込をしていた場合は、施策2・3でそのまま同じ決済サービスのポイントをもらうことも、変更することもできる。ただし、その場合も、施策2・3でもらえるポイントは同じ決済サービスのものとなる。
健康保険証としての利用申込で7,500円分のポイント
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう申込み、マイナポイントの申込をすると、7,500円分のポイントがもらえる。
健康保険証として利用申込をすることで、専用サイト「マイナポータル」で特定健診情報や薬剤情報・医療費の確認、確定申告の医療費控控除ができるようになる、窓口への書類持参が不要になるなどのメリットがある。
公金受取口座の登録で7,500円分のポイント
自身の預貯金口座を国(デジタル庁)に登録して、マイナポイントの申込をすると、7,500円分のポイントがもらえる。
公金受取口座の登録で、緊急時の給付金等の申請において、申請書への添付書類や行政機関における講座確認作業等を省けるメリットがある。
マイナポイント申込方法
マイナポイントへの申込は、スマートフォンやPCで行える。申し込みの際には、以下の3点を用意しよう。
- マイナンバーカード
- 数字4桁のパスワード(暗証番号)
→マイナンバーカード申請時or受取時に自分で設定したもの - マイナポイントの申込をする決済サービスID/セキュリティコード
第2弾ではじめて申し込む場合も、第1弾ですでに申し込み済で第2弾で新たな施策に申し込む場合も、手続きの基本の流れは同じだ。
スマートフォンで申し込む場合、iPhoneはApp Storeで、AndroidはGoogle Playで「マイナポイント」アプリをインストールする。PCで申し込む場合は、「マイキーID作成・登録準備ソフト」をインストールの上、ICカードリーダーライターを用意しよう。
なお、申込手続きの中で暗証番号を入力する必要があるが、パスワードは3回連続して間違うと不正防止のためのロックがかかるので注意しよう。ロックの解除は、居住地域の市町村窓口でパスワードの再設定を行う必要がある。
スマートフォンで申し込む場合
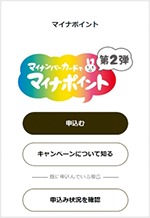
画像引用:マイナポイントの申込方法
1.「マイナポイント」アプリを起動>「申込む」をタップ
2.「はじめる」をタップ>数字4桁のパスワード(暗証番号)を入力
3. マイナンバーカードをスマートフォンで読み取る
4. 施策1~3のうち申し込むものにチェックを入れて次へ
5. マイナポイントをもらう決済サービスを選択する
※第1弾で申込済の場合は、その際に選択した決済サービスが表示される。
※決済サービスのアプリや店頭からしか申込ができない場合あり。
6. 選択した決済サービスについて確認する
7. 「決済サービスID(必須)、セキュリティコード(必須)、電話番号下4桁(任意)」を入力
8. 申込内容を確認し、申し込む
9. 利用規約を確認
10.申込完了を確認、施策3の登録が未完了の場合は手続きができるメッセージ表示あり
PCで申し込む場合

画像引用:マイナポイントの申込方法
1.「マイナポイント申込みサイト」を開く※Microsoft EdgeまたはGoogle Chromeを利用する場合、拡張機能追加が必要
2. マイナンバーカードをカードリーダライタで読み取る
3. 数字4桁のパスワード(暗証番号)を入力
4. 施策1~3のうち申し込むものにチェックを入れて次へ
5. マイナポイントをもらう決済サービスを選択する
※第1弾で申込済の場合は、その際に選択した決済サービスが表示される。
※決済サービスのアプリや店頭からしか申込ができない場合あり。
6. 選択した決済サービスについて確認する
7. 「決済サービスID(必須)、セキュリティコード(必須)、電話番号下4桁(任意)」を入力
8. 申込内容を確認し、申し込む
9. 利用規約を確認
10.申込完了を確認、施策3の登録が未完了の場合は手続きができるメッセージ表示あり
全国7万カ所に設置、マイナポイント手続きスポット
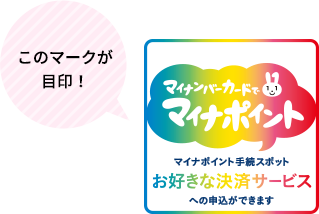
画像引用:マイナポイント手続スポットで申込み
スマートフォンやPCでの手続きが難しい場合、全国約7万カ所に設置されている、「マイナポイント手続きスポット」という端末を利用して申込を行うこともできる。
マイナポイント手続きスポットの設置個所は、以下のようにスーパーや家電量販店、郵便局、携帯電話ショップなどさまざま。これらの対応箇所には上記のマークが掲示されている。
- イオンの総合スーパー、一部の食品スーパー
- ビックカメラグループ(ビックカメラ、コジマ、ソフマップ)
- ヤマダデンキグループ(ヤマダデンキ、ベスト電器)
- 郵便局
- auショップ
- ソフトバンクショップ、ワイモバイルショップ
- ドコモショップ
また、市町村の窓口でも対応している箇所がある。マイナポイント公式サイトでは、手続きスポットの検索が可能だ。
対象キャッシュレス決済サービス
マイナポイント第2弾の対象となる決済サービスは以下の通り(2022年7月時点)。
電子マネー
プリペイドカード
QRコード
クレジットカード・デビットカード
マイナンバーカードの交付方法
すでにマイナンバーカードを持っている人は必要ないが、まだマイナンバーカードを持っていない人は、まず交付申請を行おう。
マイナンバーカードの交付には、「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」が必要。
「通知カード」は、マイナンバー制度開始時に、住民票登録の住所に簡易書留で送付された、マイナンバー通知のための紙製のカード。マイナンバーのほか、氏名・住所・生年月日・性別が記載されている。
「個人番号カード交付申請書」は、通知カードに同封されている書類だ。この2点を準備して、次のいずれかの方法で申請を行う。
- 郵送による申請
- オンライン申請(スマートフォンまたはPCによる申請)
- まちなかの証明写真機による申請
郵送による申請方法
交付申請書の必要な項目を記入したら、交付申請書と一緒に同封されていた送付用封筒(宛先が印字されている)か、普通の封筒で個人番号カード交付申請書受付センター宛に郵送する。
なお、交付申請書には、原則、住民票記載の氏名・住所があらかじめ印字されている。誤りや変更などで現在の氏名・住所と異なる場合、その交付申請書は利用できないので、現住の市町村窓口に問い合わせよう。
オンライン申請の方法
オンライン申請サイトにて手続きを行う。スマートフォンの場合、交付申請書に記載されているQRコードを読み取ることでアクセスできる。
オンライン申請サイトでは、申請書ID(半角数字23桁)/氏名/メールアドレスの入力を求められる。そして、入力したメールアドレス宛に、申請者専用ウェブサイトが案内される。
なお、QRコードを読み取ってオンライン申請サイトにアクセスした場合、申請IDはあらかじめ入力された状態となっている。
申請者専用ウェブサイトでは顔写真を登録した上で、生年月日/電子証明書の発行希望有無/氏名の点字表記希望有無を入力、送信する。
なお、登録する顔写真には条件があるので注意しよう。最近では写真館や証明写真機でも電子データをもらえる場合があるので、そういったデータが手元にあると便利だ。
証明写真機による申請方法
街中にある証明写真機のうち、以下のメーカーのものがマイナンバーカード交付申請に対応。各メーカーのサイトより、設置場所や対応状況、申請方法を確認できる。
株式会社DNPフォトイメージングジャパン
日本オート・フォート株式会社
富士フイルム株式会社
三吉工業株式会社
株式会社プラザクリエイト
証明写真機での申請には、交付申請書(QRコード付き)が必要。写真機によって多少違いはあるが、基本的には、マイナンバーカード交付申請のメニューを選択して、交付申請書のQRコードを読み込ませ、案内に従って必要事項を入力する。
証明写真機に出向く手間はかかるが、写真を撮ってその場で申請ができるため、実は意外と簡単な申請方法だ。
マイナンバーカード交付申請時の注意点
電子証明書はマイナポイント利用に必須
マイナンバーカードでは以下2種類の電子証明書が利用できる。
- 署名用電子証明書:英数字6文字以上16文字以下・電子文書の作成・送信時の本人証明
- 利用者証明用電子証明書:数字4桁・ウェブサイトや専用端末などログイン時の本人証明
マイナポイント事業を利用したい場合、電子証明書が必須となる。マイナンバーカード交付申請の際に、「署名用電子証明書」「利用者証明用電子証明書」発行有無で、必ず発行希望を選択しよう。
また、暗証番号入力が必要な場面で、3回連続(署名用電子証明書は5回連続)で間違えるとロックがかかってしまう。ロックがかかった場合、または暗証番号を忘れた場合は、市区町村の窓口で暗証番号の再設定が必要となるので注意したい。
通知カード・交付申請書をなくした場合
交付申請書をなくした場合、マイナンバーカード公式サイトからダウンロードが可能。ただし、その場合は郵送による申請しか行えない。
これは、オンラインや写真証明機による申請では、通知カードにひもづいて申請書にあらかじめ記載されているIDやQRコードが必要なためだ。
通知カードをなくした場合は、現住の市区町村窓口で再発行の手続きが可能。ただしその際には、警察署または交番に遺失物届を提出し、その受理番号の控えが必要になる。
受取は約1カ月後、市区町村窓口にて
マイナンバーカードの交付申請を行うと、概ね1カ月で現住の市区町村から交付通知書が発送される。
マイナンバーカード自体は郵送されず、原則、現住の市区町村窓口での受け取りとなる。通知書に交付場所が記載されているので、以下3点を持って受け取りに行こう。
- 交付通知書
- 通知カード
- 本人確認書類
マイナンバーカード発行時に、通知カードは市区町村に返却することになる。
地域によって多少違いはあるだろうが、市区町村の窓口は基本的に平日の日中なので、交付通知書が来てもすぐに取りに行けない可能性もある。マイナンバーカードの申請は余裕をもって早めに行うようにしよう。
現時点で手数料はかからない
マイナンバーカードの交付手数料は、当面の間無料とされている(本人の責による再発行の場合を除く)。ただし、今後、マイナンバーカードが普及するにつれ変更となる可能性があるため、無料の今のうちに発行しておいたほうがお得だ。
なお、マイナンバーカードを紛失した場合、市区町村窓口で再発行が可能だ。その際の手数料の有無や金額は市区町村によって異なる。
どの決済サービスがお得?ポイントの二重取りも可能
マイナポイント事業でもらえるポイントは、どの決済サービスを選んでも変わらない。
ただ、クレジットカードやQRコード決済などは、マイナポイントとは別に独自のポイント還元制度を運営しているサービスが多い。そのため、マイナポイントと合わせてポイントの二重取りが可能だ。
ただし、いくら還元率が高いサービスでも、ほとんど利用しないサービスでは意味がない。マイナポイントで選べる決済サービスは1つだけなので、以下のポイントをおさえて、最もお得になるサービスを選ぼう。
- 利用頻度が高い決済サービス
- その決済サービス独自のポイント還元がある
クレジットカードは安定のポイント還元
マイナポイント事業の対象決済サービスには、楽天カードや三井住友カードなど、多くの人に利用されるクレジットカードが含まれている。
キャッシュレス決済にあまり詳しくない方や、詳しく調べる時間がない方は、マイナポイントに普段使いのクレジットカードを登録することをおすすめする。
クレジットカードにもキャンペーンはあるが、その内容は年会費無料や入会時のポイント付与などが多く、通常のポイント還元率が頻繁に変わることはない。
そのため、安定してポイント還元を受けることができるのだ。楽天カードなどの還元率が高いカードを登録すれば、マイナポイント事業と合わせて25%以上の高還元率が実現できる。
条件を満たせばかなりお得なQRコード決済
マイナポイント事業の対象決済サービスには、PayPay、楽天ペイ、d払い、au Payなどの主要なQRコード決済サービスが含まれている。
QRコード決済サービスは、支払い方法や期間限定のキャンペーンによりポイント還元率が変動しやすい。そのため、条件を満たすことができればかなりの高還元率になる可能性がある。
クレジットカードを持っていない人や、スマホ決済の各サービスの条件を確認してお得さを追求するのが苦にならない人などは、マイナポイントにスマホ決済を登録するのが良いだろう。
PayPay インストールはこちらから【PR】

子どもでもマイナポイントをもらえる?
マイナンバーカードは、15歳以上は本人が、15歳未満は法定代理人が申請することになる。マイナポイント予約時に必要な暗証番号(利用者証明用電子証明書)も、15歳未満は法定代理人が設定する。
そのため、法定代理人であれば15歳未満のマイナンバーカードを利用してマイナポイントの利用が可能だ。なお、署名用電子証明書は実印と同じ効力を持つため、15歳未満では設定できないが、マイナポイントには必要ないため影響はない。
マイナポイントの規約では、マイナポイントの申込は、本人名義のキャッシュレス決済サービスへ申し込む必要がある。しかし、未成年者のマイナポイントについては、法定代理人名義の決済サービスをポイント付与対象として申込むことができる。(マイナポイント利用規約第5条)
ただし、同じ決済サービスに複数人のマイナポイントを合算して付与することができないため、法定代理人名義の異なる決済サービスを選択する必要がある。
マイナンバーカード発行のメリット
誰でも簡単に持てる
マイナンバーカードは、日本に住民票のある人なら誰でも取得できる(15歳未満は法定代理人による申請が必要)。
表面には顔写真付きで住所・氏名が記載されているので、一枚で本人確認が可能だ。ただし、カード裏面に記載されたマイナンバーは、悪用を防ぐため、むやみに人に知られないよう注意が必要だ。
本人確認の身分証明書としてよく利用される運転免許所は、18歳以上でないと取得できないし、20万円前後の費用を払って、試験に合格しないと取得できない。
保険証は誰でも持てるが、顔写真がないため、身分証明書としては十分とはいえない。パスポートも、住所が印字されていないため、実は国内での身分証明書としては不十分なことがある。また、発行には1~2万円前後の費用がかかる。
行政サービス、民間のオンライン取引に使えて便利
マイナンバーカードは、以下のような行政サービスやオンライン申請、民間のオンライン取引に利用できる。
- e-Taxやマイナポータルなど各種行政手続きのオンライン申請
- オンラインバンキングなど民間の各種オンライン取引
- 行政が提供するさまざまなサービスに1枚で対応
- コンビニなどでの各種証明書(住民票、印鑑登録証明書など)取得
特に、e-Taxやコンビニなどでの各種証明書の取得に利用できるのは、利便性が高い。
マイナンバーカード発行のデメリット
セキュリティ面の不安が不安?
マイナンバーカードを持たない理由としてよく挙げられるのが、セキュリティ面の不安だ。
ただ、マイナンバーカードを発行していなくても、マイナンバーは存在している。そして、マイナンバーの提示が必要な場合、通知カードにより示すことになる。
そのため、マイナンバーカードの有無によって、セキュリティ面に大きな違いはない。むしろプラスチック製のマイナンバーカードと紙製の通知カードとでは、通知カードのほうが紛失の可能性が高く、セキュリティ面に不安がある。
マイナンバーカードのセキュリティ対策
マイナンバーカードでは、セキュリティ対策として以下のような対策をとっている。
- 紛失時は24時間365日対応のコールセンターで一時停止可能
- 顔写真付により第三者のなりすまし防止
- 文字レーザーや彩紋パターンによる券面偽造防止
- ICチップに、税金・年金関係などプライバシー性の高い情報を記録しない
- 電子証明・アプリごとに暗証番号設定、一定回数以上の間違いでロック
- セキュリティの国際基準「ISO/IEC15408認証」取得
なお、マイナンバーカードを再発行する場合、基本的にマイナンバーは変更されないが、個人番号が漏えいして不正に用いられる恐れがある場合は、所定の手続きによりマイナンバーも変更可能となる。
発行までに時間がかかり、受け取りがやや面倒
マイナンバーカードを発行したほうが良いのはわかっていても、発行に踏み切れない理由として、手続きを面倒に感じることがあるのではないだろうか。
通知カードと交付申請書さえあれば比較的簡単に交付申請はできるのだが、いずれかをもっていない場合は、たしかに手続きに少し手間がかかる。
また、クレジットカードなどと違い、カードが郵送されてくるのではなく、交付通知書を受け取ってから市区町村の窓口に受け取りに行かなければならない。
市区町村の窓口は基本的に平日日中のみの対応となることが多いため、このあたりにも面倒さを感じるのではないだろうか。
いずれ必要なら今発行すべき
マイナンバーカードは国として積極的に発行を推進している。そのため、いずれほとんどの人がもつよう制度や政策などが進められていくものと予想される。
それならば、無料で発行でき、マイナポイント事業を利用できる今のうちに発行しておいたほうがお得だ。
セキュリティ面の不安も、マイナンバーカード発行の有無によって変わることはほとんどないし、むしろマイナンバーカードを発行したほうがマイナンバーのセキュリティ面では安心だ。